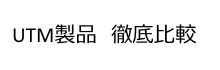なぜ大手飲料メーカーがランサムウェア攻撃を受けたのか? ─ アサヒビールの事例から学ぶ
ランサムウェアとは何か
ランサムウェアとは、“企業のシステムやデータを人質に取る”不正な攻撃手法です。攻撃者はコンピュータに侵入し、重要なデータを暗号化したり、アクセスできなくしたり、さらに「このデータを外部に流出させる」と脅すことで、企業に身代金の支払いを要求します。被害を受けると、ただパソコンが使えなくなるだけではなく、出荷/受注/顧客対応など企業の根幹を担う業務が止まる可能性があるのです。
つまり、ランサムウェアは「IT部門だけの問題」ではなく、「ビジネスを止める可能性がある、企業経営のリスク」なのです。
なぜアサヒビールが狙われたのか
今回、国内最大手の飲料メーカーであるアサヒビールがランサムウェア攻撃を受けた背景には、以下のような理由があります。
- 規模が大きく、製造・物流・出荷・販売の仕組みを広範囲に持っており、「止まったときの影響が大きい」ため攻撃者にとって魅力的な標的でした。
- 製造現場(工場)から出荷・注文・コールセンターに至るまで複数の部門を網羅するシステムを抱えており、ネットワークが“広く繋がっている”構造であった可能性があります。
- サプライチェーン・物流を止めることができれば、外部へのインパクト(例えば小売店の在庫不足など)も広がるため、交渉力を持ちやすいという傾向があります。
- また、報道によると攻撃を主張したグループが「約9,300ファイル、約27ギガバイトのデータを持ち出した」と主張しており、単なる無差別攻撃ではなく「情報を持ち出して脅す」タイプの攻撃であることが示唆されています。
このように、アサヒビールは“攻撃者が狙いやすい条件”を複数備えていたと考えられます。
アサヒビールがどういった経路でランサムウェア攻撃を受けたのか
公式発表・報道から明らかになっている範囲で整理します。
侵入・初期アクセス
アサヒビールのシステムに攻撃者が不正アクセスし、初期侵入したと推定されます。公式には「システム障害発生」「不正なデータ移転の可能性」といった記述があります。
横展開・業務停止
侵入後、製造工場・出荷システム・受注・コールセンターなど複数業務に影響が出ました。例えば、国内6工場の生産が停止、出荷・注文が停止されたと報じられています。
データ持ち出し・暗号化・脅迫
攻撃グループ側が「約9,300ファイル(約27 GB)を持ち出した」と主張。アサヒビール側も「不正なデータ移転の可能性を確認している」としています。実際、出荷用システムがダウンしたり、紙・ファックス運用に切り替えられたりするなど、通常のシステム運用ができない状態になりました。
業務復旧・被害対応
アサヒビールは国内6工場の生産を10月2日(システム障害第一報:2025年9月29日)から再開しましたが、完全復旧には時間を要しており、出荷量も通常時より低下しているとの報道があります。業務停止から手作業運用への移行が余儀なくされました。
このように、侵入から業務停止・被害拡大・復旧という流れをたどっています。
傾向として、「攻撃者はまず侵入し、横展開・停止を誘発、そしてデータの持ち出しを行い、停止したことで交渉の余地を持とうとする」という典型的なランサムウェア攻撃プロセスが現れています。
ランサムウェア対策
では、こうしたリスクに備えるために、企業としてどのような対策を講じるべきかを整理します。ネットワークセキュリティに詳しくない方でも理解しやすいよう、ポイントごとに解説します。
定期バックアップと迅速な復旧体制
重要なデータや業務システムを定期的にバックアップし、万が一システムが使えなくなったとしても業務を継続できるように備えましょう。バックアップはネットワークから切り離した場所やクラウドに保管することが望ましいです。また、復旧手順をマニュアル化・訓練しておくことがポイントです。
ネットワークの分割・セグメンテーション
製造システム(工場設備、制御系)と業務系システム(受注・出荷・管理)を明確に分離し、それぞれネットワークを区切ることで、もし一部が侵害されたとしても被害が広がりにくくなります。アクセス権限も「必要最小限」に設定することで、攻撃者が自由に動ける範囲を狭められます。
侵入防止・入口対策(初期アクセス抑止)
多くのランサムウェア攻撃は、フィッシングメールや脆弱なリモート接続・委託先経由で初期侵入が始まります。社員への教育(怪しいメールを開かない/添付ファイルを不用意に開かない)、多要素認証(MFA)の導入、不要なネットワークポートやサービスを閉じる、システムを常に最新のパッチで保守する、といった基本対策を徹底しましょう。
検知と対応(モニタリング・インシデント対応)
侵入されたとしても早期に気づける体制があれば、被害を最小化できます。ネットワーク・端末ログを収集・分析し、異常な通信や挙動を検知できるようにすること、さらに攻撃発見後に迅速に封じ込め(ネットワーク切断、被害範囲の隔離)できる体制を整えておくことが重要です。また、外部の専門機関との契約・連携をあらかじめ結んでおくと、いざという時に頼りになります。
事業継続計画(BCP)・代替運用手段
万一システムが停止したとき、手作業で注文処理する、紙・ファックス・電話対応に切り替えるといった代替手段をあらかじめ想定しておくべきです。今回のアサヒビールのケースでも、手作業・紙・ファックス対応に切り替えたという報道があります。こうした“緊急対応手段”を準備しておくことで、被害拡大を防げます。
また、取引先・物流・出荷というサプライチェーン全体での影響を想定し、「もし供給が止まったらどうするか」を取引先と協議しておくことも推奨されます。
データ漏えい対応・法令遵守
ランサムウェア攻撃では、「暗号化されてアクセスできない」だけでなく「データを外部に持ち出された/流出された」というリスクもあります。アサヒビールも「不正なデータ移転の可能性」を公表しています。万が一漏えいが確認された場合には、個人情報保護法やその他法令・監督機関の規定に基づき、速やかに対応・通知を行う必要があります。さらに、身代金を支払うかどうかの判断も含めて、あらかじめリスク・コストを分析しておくことが重要です。
まとめ
今回、アサヒビールの事例を通じて改めて見えてきたのは、ランサムウェア攻撃がもはや「情報システム部門だけの問題」ではなく、「企業のビジネスを止める可能性のある重大な経営リスク」であるということです。
製造・物流・出荷という物理的なプロセスを持つ企業では、攻撃の影響が目に見える形で広がり得ます。だからこそ、ネットワークセキュリティ・システムのセキュリティ・サプライチェーン・業務継続をトータルに見た備えが不可欠です。
「うちの会社は中小だから大丈夫」と思うことが、実は大きな落とし穴となることもあります。中小企業でも取引先・サプライチェーンを通じた被害の波及があります。
このブログを読んでくださった皆さまには、ぜひ以下の問いを持って頂ければと思います:
- 自社では業務システムのバックアップを定期的に取り、復旧手順を用意していますか?
- ネットワークはどこまで分割・制御されており、不要なアクセスは除かれていますか?
- 社員にはフィッシング対策・リモートアクセス対策の教育が行われていますか?
- もしシステムが停止したら、手作業や代替運用で業務を継続できますか?
- データ漏えいが発生した際の対応体制(通知・法令対応・取引先対応)は整っていますか?
このような“自分事”としての意識こそが、いざという時に被害を最小化し、会社を守る力になります。
ランサムウェア対策=ネットワークセキュリティの強化は、特別な業界だけの話ではなく、すべての企業にとって今や「必須」の課題です。